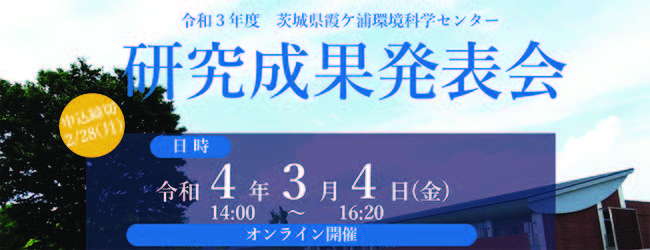トップページ > 調査・研究 > 令和3年度成果発表会
令和3年度成果発表会
- 開催日時:令和4年3月4日(金曜日) 14時00分 から 16時20分 まで
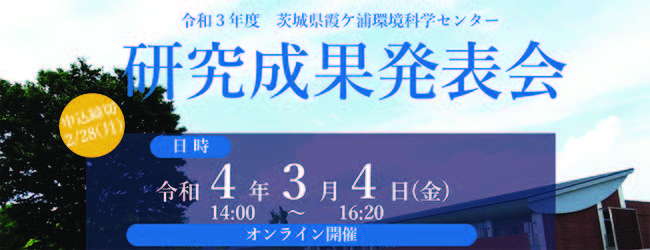
- 開催形式:Zoomを利用したオンライン開催
- リーフレット

概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン(Zoomミーティング)による開催としました。センター長の福島から「浅い湖沼:霞ヶ浦の水質特性」が紹介されたほか、湖沼環境研究室の研究成果を口頭発表するとともに、大気・化学物質研究室の研究成果をポスターにまとめ、ホームページで公開しました。参加者から多くのご質問・意見があり、活発な質疑応答となりました。
特別講演
<Q&A>
Q:トリプトン濃度の経年的な増減は、無機態SSの増減が主体と理解して良いですか。無機態SSの経年的な成分変化はありますか?
A:トリプトンは無機態粒子とデトリタスの和ですが、ご指摘のようにその濃度の経年的な増減は無機態粒子(無機態SS)濃度の増減が主体と考えています。無機態粒子の成分については、チタン、アルミニウム等の含量が測定された時期もありますが、経時的な変化は調べられていません。表層底泥の無機成分の組成と近いと考えられますが、その経時変化も調べられてはいません。サンプルの保管が重要と考えます。
研究発表
- 夏季の北浦における水温成層及び貧酸素水塊の形成と消失条件の検討
湖沼環境研究室 主任研究員 北村 立実
<Q&A>
Q:水温成層ができる条件はどのようなものですか?
A:外部から何か入ってきたのではないかと考えています。
Q:湖上の風速とは、湖水面から何m上で計測されたものですか?
A:10m程度です。
Q:PO4−Pの日変化について報告されていますが、成層期間中により細かいサンプリングなどは実施していますか?
A:行っています。
Q: 貧酸素塊ができてから、PO4−Pがすぐに溶出が始まる場合としばらくして溶出が始まる場合がありますが、何が原因ですか?例えば、植物プランクトンが消費している場合はすぐにPO4−P濃度が上がらないということですか?
A:難しいなと思っていて、明らかにはなっていません。底層の還元状態に依存するのではないかと思います。
Q:りんの測定ですが、貧酸素水塊層界の鉄、マンガン等との錯体濃度や生成速度等を測定する計画はありますか?
A:計画はありません。
- 巴川・鉾田川流域における窒素負荷量の推移と河川水質への影響
湖沼環境研究室 主任 大内 孝雄
<Q&A>
Q:地下水の硝酸態窒素のモニタリングデータも上昇傾向にありますか?
A:対象流域における地下水の窒素濃度は全体的に高いですが、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の調査が本格的に開始されたのは2000年代以降であり、その範囲では顕著な上昇傾向は見られません。
- 県内3地区のハス田群の環境負荷とその改善策の提案
湖沼環境研究室 主任研究員 佐野 健人
<Q&A>
Q:なぜ、ハス田はいつも水を張っているのですか?
A:水を張っておくことで腐敗病の防止になっています。また、隣の圃場に水が漏れやすいので、漏れても大丈夫なように水を多く入れています。
- 浄化導水による新川の水質変化
湖沼環境研究室 流動研究員 古川 真莉子
<Q&A>
Q:冬季の導水では、農業排水路の流量の6倍以上の浄化導水が流れていて水質改善効果があったということですね。春季で浄化効果を確保するために、冬季と同様に農業排水路の流量の6倍流せば良いのではないでしょうか?
A:浄化導水の水量はポンプの出力による限界があるため、流量を6倍にすることはできません。しかし、長期間流すことで水質改善効果が出ると考えられます。
- 近年の牛久沼の水質変化とその要因
湖沼環境研究室 主任 長濱 祐美
<Q&A>
Q:植物プランクトンの相については2015年度以降、変化がありますか?
A:牛久沼は年間を通じてAulacoseira属をはじめとした珪藻が優占していて、この傾向は変わっていません。しかし、春先に別の種類が優占することが時々あります。2015年度以降、この春先に増殖する珪藻類の種類がStephanodiscus属からSurirella属に変わってきているようですが、CODに与える影響はわかりません。
ポスター発表
[大気・化学物質研究室]
<問い合わせ先>
茨城県霞ケ浦環境科学センター 湖沼環境研究室
〒300-0023 茨城県土浦市沖宿町1853番地
TEL:029-828-0963(直通)
FAX:029-828-0968
※月曜日(祝日の場合は翌日)は休館日となっております。